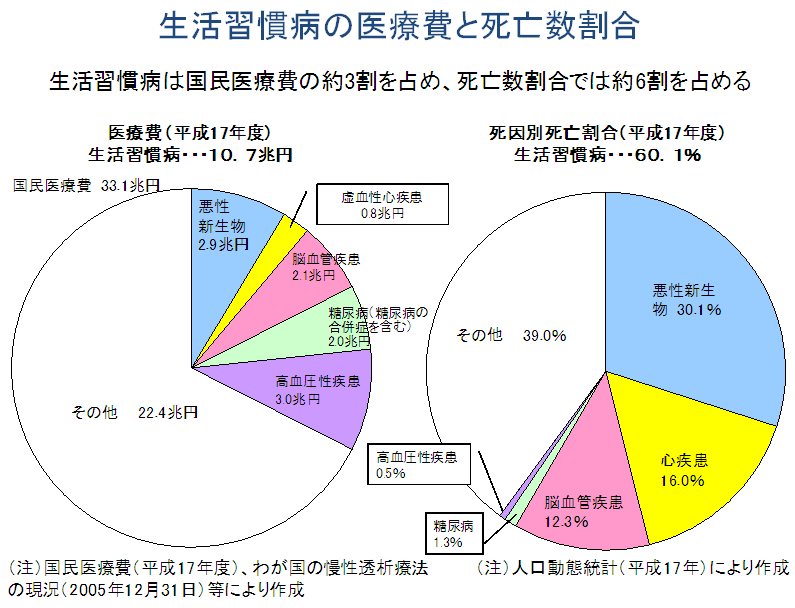医療費抑制を狙った政策強化と市場の成長期待
セルフメディケーション(軽い体調不良を自分で手当てし、健康管理に主体的に取り組むこと)は、近年注目されています。背景には高齢化や生活習慣病の増加、そして医療費の膨張があり、国としても医療費抑制や医療資源の有効活用のため推進しています。
特に!最近また!『セルフメディケーション』がビジネスキーワードとして再沸騰しています。ご存じでしたか?
これは「セルフメディケーション税制」の改正・延長や、対象医薬品の拡大議論など、政策的な動きが活発化しているからです。2026年には税制の対象をすべてのOTC医薬品・検査薬に拡大する要望も出ており、これが話題再燃の一因です。
市場面では、OTC医薬品(市販薬)市場が高齢化や健康意識の高まりで今後も成長が見込まれ、デジタルヘルスやパーソナライズド製品など新たなサービスも増えています。
要約すると、セルフメディケーションが再び注目されているのは、「医療費抑制を狙った政策強化」と「市場の成長期待」が重なったためです。
実際問題、医療費抑制効果は出ているの?
実際にセルフメディケーションによる医療費抑制効果は一定程度確認されています。たとえば、セルフメディケーション税制の導入により、患者の受診頻度が1.8%、医師の処方量が6.0%、薬剤費が5.8%減少したというデータがあります。ただし、全体の薬剤費抑制効果は−0.26%と限定的との試算もあり、劇的な医療費削減には至っていません。
また、セルフメディケーション全体では3,000億円以上の効果があるとも言われていますが、これは潜在的な効果額であり、今後の普及や制度設計によってさらに効果が拡大する可能性があります。

薬局やドラッグストアの売上アップに?
セルフメディケーションの推進やセルフメディケーション税制の導入は、実際に薬局やドラッグストアのOTC(一般用医薬品)売上アップにつながっています。
たとえば、セルフメディケーション税制が始まった2017年1月のドラッグストアにおけるOTC販売額は前年同月比で7.6%増加し、その後も市場全体で年率4.8~7.3%の伸びを示しています。また、OTC医薬品の生産・販売シェアも増加傾向にあり、ドラッグストアでの存在感が高まっています。
一方で、薬局やドラッグストア間の競争も激化しており、物販やサービスの差別化が求められています。つまり、セルフメディケーションは売上増加の要因となっているものの、競争環境も厳しくなっているのが現状です。
薬局の顧客満足度に与える影響は?
セルフメディケーションは薬局の顧客満足度にプラスの影響を与えています。特に、薬剤師が丁寧で分かりやすい説明や相談対応を行うことで、顧客の満足度が高まる傾向が明らかになっています。「とても満足」「少し満足」と感じる人が多く、薬剤師の積極的な関与がセルフメディケーション推進と顧客満足度向上の両方に寄与しています。
一方で、薬剤師の説明が不十分だった場合や相談しにくい雰囲気があると、満足度が下がることも示されています。顧客は「相談しやすさ」「親身な対応」「わかりやすい説明」を重視しており、薬局側の姿勢やサービスの質が顧客満足度に直結しています。
まとめると、セルフメディケーションの推進は、薬剤師の専門性とコミュニケーション力を活かしたサポートがあってこそ、顧客満足度の向上につながるといえます。
ドラッグストアの競争力にどう関係するの?
競争力強化のポイント
- セルフメディケーションの推進は、ドラッグストアが「健康管理の拠点」として社会的に期待される役割を高め、他の小売業態との差別化につながっています。
- OTC医薬品や健康関連商品の販売強化により、ドラッグストアは専門性を活かしたサービス提供が可能となり、顧客からの信頼やリピート利用を促進します。
- 薬剤師やスタッフによる健康相談・アドバイスの充実は、セルフメディケーションを支援し、顧客満足度や店舗へのロイヤルティ向上に寄与します。
市場拡大と他業界との差別化
- セルフメディケーション対応領域の拡大は、食品やスポーツ業界など他分野とのコラボレーションも促進し、総合的な健康サポート店舗としての競争力を強化します。
- 国の政策的後押しや健康志向の高まりも追い風となり、ドラッグストアの市場規模拡大や新規顧客獲得につながっています。
薬局の売上に与える具体的な影響は?
- 調剤薬局がOTC医薬品や健康食品などの物販を強化することで、「そのときの売上」だけでなく、患者との信頼関係構築による「将来的な売上増加」が期待できます。
- 薬剤師が患者の症状や生活習慣を把握し、適切なOTC医薬品や健康商品を提案することで、継続的な来局や購入率のアップにつながります。
- セルフメディケーションのサポートを通じて薬局が「健康相談の場」として認識されると、他店との差別化が進み、リピーター獲得や新規顧客の増加に寄与します。
- 一方で、物販スペースや在庫管理、スタッフの知識向上などの課題もありますが、総じて売上増加の効果が見込まれます。
医療費の抑制にどのように寄与するの?
- セルフメディケーションは、軽度な不調を自分で市販薬(OTC医薬品)などで対処することで、医療機関の受診や医師の処方薬利用を減らし、医療費の抑制に寄与します。
- 具体的には、医師の処方薬をOTC医薬品に置き換えることで、医療費削減効果は年間約3,000億円以上と推計されています。また、生活習慣病の予防や重症化防止にもつながり、国民医療費の約3割を占める生活習慣病関連コストの低減にも貢献します。
- 注)国民医療費の約3割を占めるのは「生活習慣病」による医療費であり、セルフメディケーションが注目される大きな理由もここにあります。生活習慣病(高血圧、糖尿病、脂質異常症など)は長期間にわたり治療や管理が必要で、医療費全体に占める割合が非常に大きいです。セルフメディケーションの推進によって、こうした生活習慣病の予防や重症化予防が期待できるため、医療費抑制の効果も大きくなると考えられています。下記の画像(厚生労働省)をご覧ください。
- さらに、セルフメディケーション税制などの政策的支援により、個人の医療費負担軽減や節税効果も生まれています。このように、セルフメディケーションは医療費全体の適正化に大きな役割を果たしています。
生活習慣病の予防にどのように寄与するの?
- 自分の健康状態や生活習慣を日頃からチェックし、適度な運動・バランスの取れた食事・十分な睡眠を心がけることで、生活習慣病の発症リスクを下げます。
- 健康診断や家庭での血圧・体重測定などを活用して早期に異変に気付き、必要に応じて生活習慣を見直すことで、重症化を防ぎます。
- 軽度な不調や初期症状を市販薬やセルフケアで対処することで、病気の進行や重症化を予防し、結果的に医療機関での高額な治療や入院を減らします。
- このように、セルフメディケーションは日常的な健康管理を通じて生活習慣病の予防・重症化防止に大きく貢献します。
となるとデメカルも同じように貢献可能では?
デメカルのような指先採血・郵送血液検査サービスもセルフメディケーションの一環として、生活習慣病の予防や早期発見に大きく貢献できます。理由は以下の通りです。
- 自宅で簡単に血液検査ができるため、忙しい人や病院に行きづらい人でも定期的な健康チェックが可能になり、生活習慣病のリスクを早期に把握できます。
- 検査結果をもとに自分の生活習慣を見直したり、必要に応じて医療機関を受診するなど、主体的な健康管理につながります。
- 継続的なセルフチェックは、無自覚に進行しやすい生活習慣病の重症化を防ぐうえで非常に有効です。
最後にひとこと
最近「セルフメディケーション」というキーワードが市場を駆け巡っています。テレビCMでも、各企業のPR文句としても頻出してきました。
デメカル郵送血液検査サービスは、セルフメディケーションの一角を担うことができると同様に、健康意識の向上・生活習慣病の予防・医療費抑制に大きく貢献できるヘルスケア・ソリューションです。